|
|
|
|
そばな高原鉄道の橋梁 山中の庭園鉄道では「本物」の山や谷を克服しなければなりません。したがって,橋梁も景観のためというよりは,橋梁本来の役割を果たすために架けています。 窪地を横断するため(高架橋),通路の頭上を通過するため(跨道橋),排水溝を跨ぐため(橋梁),それぞれの設置目的に合わせてデザインだけではなく実用性も兼ね備えていなければなりません。 |
|
| <1> | |
第1橋梁 第1橋梁は高さ2mの築堤と高さ1.6mの高架線3との間に架けられている長さ2.13mの鉄橋です。 築堤と高架線を直接つなぐよりも工事が容易で,橋梁によって地形の変化を際立たせ実際の鉄道景観に近い感じを出すことを目的としています。(右写真 ) 橋梁の形式を上路デッキガーダー橋に決めた理由は ● どこにでもある「普通」の鉄橋を作りたい。 ● 実際の鉄道でもこの様な条件の所にはデッキガーダー 橋が架けられている。 ● 実物に近い縮尺比で架橋できる 。 ● 曲線区間内の橋なのでガーダー桁を「く」の字にすれば自然な姿でカーブに対応できる。 |
|
|
下図は構想段階の第1橋梁です。実際に製作した第1橋梁はガーダー桁2連に「小川を渡る小橋(小海線の橋梁)を追加し ,3連としました。 |
|
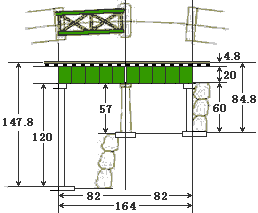 第1橋梁(始発駅) 第1橋梁(始発駅)細部の設計を始めてみると,都内や近くの多摩川で撮った写真では不明の箇所が多く,より詳しく調べて疑問を解決することにしました。 小海線が適当と思い橋梁を見に行きました。小海線には多くのデッキガーダー橋が あり,千曲川に沿って鉄道と道路が並行していて観察には都合が良い線区でした。 小海線の橋梁を |
|
| <2> | |
第2橋梁 第2橋梁は自生しているカラマツの丸太材の利用方法として思いついた橋で,庭園鉄道と周囲の景観との調和も考えながら,試行的に作った木造の鉄道橋です。 第2橋梁は「模型」ではなく人 の乗った車輌が通過する「庭園鉄道の木造橋」をイメージしています。 |
|
|
一本の丸太をそのまま橋脚にし,鉄材を使用しない方法で造りましたので実際の鉄道の橋梁とはかなり異なったデザイン,構造になりました。 |
|
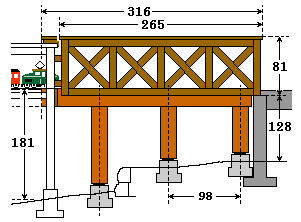 第2橋梁(始発駅) 第2橋梁(始発駅) |
|
| <3> | |
|
第3橋梁 第3橋梁は高さ2.2m,長さ1.5m(支間1.42m)で5インチゲージの橋としては小形です。架橋場所は地上7mの2階の屋根から雨水が直接落下する所で,冬には落雪の直撃を受ける箇所でもあります。 降雪地の軒下は模型の線路には手強い相手です。軒先に雨樋が付いていないため雨水が「白糸の滝」状に落ち,線路がこの水の簾(すだれ)を通り抜ける箇所は耐水性も考えなければなりません。 更に厄介なのは冬季に氷塊を含んだ落雪により線路(軌きょう)は強い衝撃力を受けます。模型 鉄道では対応が難しい条件であり,雨水や落雪に耐える構造物としてはどのようなものがよいかを考えてみました。 その結論として破損しやすい路盤や道床が無く,鉄材主体の構成になる橋梁ということになりました。 |
|
|
橋梁にすることで雨水や降雪は軌きょうの間から下に流してしまうので水捌けは完全です。問題は屋根からの落雪に対しての備えです。下記(注) 大量の落雪に対して橋梁のどの部分も強度不足にならないように頑丈な造りにします。 氷塊に対して強いのは丸木橋のような単純な棒状の形がよいので,デッキガーダー橋(上路プレートガーダー橋)としました。強度面から材料は鉄ですが腹板だけは鉄板ではなく防水性と強度に優れたアクリル板を使っています。 デッキガーダー桁は雨や雪には強いのですが軌きょうは落雪に弱いので,冬季は防護カバーを被せる必要があります。 |
|
|
第3橋梁(始発駅) |
|
|
(注)
落雪の(衝)撃力はその時の条件に左右されるので一律には決められませんが,初歩の物理≪自由落下≫の値(物体は1s間に4.9m落下し,9.8m/sの速さになる)で概略の状況が分かります。 いま,1kgの氷(雪)塊が高さ4.9mの屋根からレールに落下する場合,速さが9.8m/sで衝突し氷塊の運動量(=力積)は1×9.8=9.8Nsとなります。この氷塊がレールに衝突して0.1s間で静止するなら9.8÷0.1=98N(≒10kg重)の力を及ぼします。 重量に換算すると10kgの物体をレールに載せた状態に相当し,広い面で受け止めるなら十分耐えられます。 しかし,氷塊のように堅い角のある落下物では狭い接触面に力が働くので単位面積当たりの力にすると大きな(衝)撃力になります。部分的にハンマーで叩いた様な壊れ方をする可能性 があります。 |
|
| <3> | |
|
|
|