|
そばな高原鉄道>軌条の敷設>移線器 |
|
●車輌は2本のレール上を走らせますが,2種のゲージを同一線路に併設するときは4本レールとせず,1本のレールを共用にして3本のレールに集約する方式=《3線式デュアルゲージ》があります。この方式の線路をそばな高原鉄道でも敷設しています。 ●3線式デュアルゲージはレールを3本にできる利点がありますが,敷設する線路の形によっては《移線器》を設置しなければなりません。 |
|
|
|
|
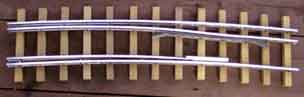 移線器は分岐器の転轍と同様にトングレールを動かして”移線”させればよいのですが,そばな高原鉄道の特殊な列車編成に対してはこの転轍方法では対応できません。 移線器は分岐器の転轍と同様にトングレールを動かして”移線”させればよいのですが,そばな高原鉄道の特殊な列車編成に対してはこの転轍方法では対応できません。そばな高原鉄道は3インチ半ゲージと5インチゲージの車輌を区別せず直接連結 します。異ゲージの車輌による混合編成では通過車輌のゲージが変わる毎に手動で「転轍操作」をすることは不可能です。 模型鉄道の安全面からは単純な構造ほど良いとも言えます。トングレールを動かす「転轍」を行わず,トングレールは固定したままでガードレールによって”移線”させる最も単純な構造の〈A形〉移線器です。 |
|
|
|
|
 〈B形〉移線器はそばな高原鉄道の車輌編成に対応出来るように考案したオリジナルの自動移線器です。 〈B形〉移線器はそばな高原鉄道の車輌編成に対応出来るように考案したオリジナルの自動移線器です。トングレールに平行な2本の鈍端レールを使用しているのが特徴で,89mmと127mmゲージの車輌による混合編成の列車に対して89mmの車輪(輪軸)のみを選択的に”移線”させます。 関連事項/私と鉄道模型(21) 自動移線器を |
|
|
移線器が必要な理由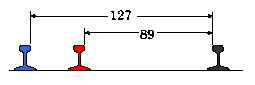 そばな高原鉄道は軌間が89mm(3インチ半)ゲージと127mm(5インチ)ゲージの車輌を走らせることができる線路になっています。 そばな高原鉄道は軌間が89mm(3インチ半)ゲージと127mm(5インチ)ゲージの車輌を走らせることができる線路になっています。特徴は図の黒のレールを共用にすることでレールを1本減らし3本のレールで2つのゲージの車輌を走らせます。 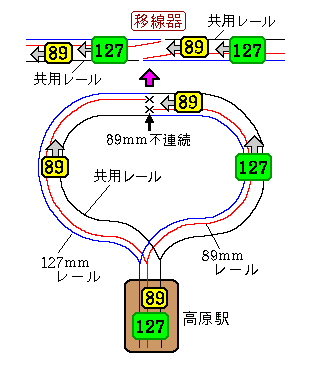 線路の敷設 には利点がありますが分岐器や転車台を設けるときには問題も生じます。 右図は高原鉄道の線路の概略図で89mmの車輌は赤と黒のレールを,127mmの車輌は青と黒のレール上を走ります。 いま,89mmの車輌が「高原駅」から出て右回りで走る場合と,左回りで走る場合の赤レールの配置を図で辿って下さい。中間点でレールに不連続が生じることが分かります。 そこで,この中間点に共用レール(黒のレール)を反対側に移す移線器を設置して問題を解決します。 ●実際の鉄道ではゲージの異なる車輌が混在することが稀な上,線路の形も移線器を必要とする線形自体が例外的なので実物を見る機会はほとんどありません。 ●模型鉄道ではデュアルゲージや移線器はそれ程特殊なものではないと思います。ただ,レイアウトの設計では移線器の設置を考慮した線路の形にすることも必要です。 移線器の参考図を |
|
|